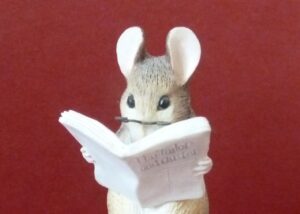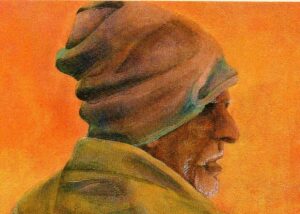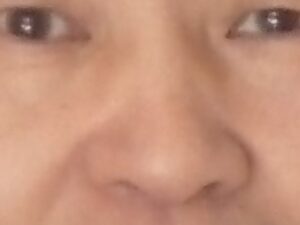Sunday Essay
人を動かす(その1)
カーネギー(Dale Breckenridge Carnegie)は1936年に著書「人を動かす(原題 : How to Win Friends and Influence People)」を出版した[1].話し方講座の […]
窯業の時代を回顧する
日本セラミックス協会の始まりは1891年に設立された窯工会だ.翌1892年には大日本窯業協会に名称変更され,1893年には代表者として品川弥二郎が初代会頭に就任した[1].品川弥二郎が死去した1900年には榎本武揚が第2 […]
熱素説と光の粒子説の興亡を振り返る
熱は物体間を移動して,物体の温度を変化させる.物体の温度が変化すれば物体は熱膨張を示す[注1].熱膨張は温度の尺度として利用される.寒暖計はその応用だ.寒暖計で温度を測定するためには温度目盛りを設定する必要がある[1]. […]
電気の世界に想いを馳せる
原子を構成する原子核も電子も電気を帯びているから現実の世界は電気に満ち溢れているのだが,電気の正体は永いこと露わにならなかった.正負の電荷はクーロン力で近づくのですぐに中和されてしまい,電気の存在はひっそりと隠されていた […]
オンネスとベドノルツに学ぶ大発見への道
デュワー(James Dewar)は1896年に水素の液化に成功し,オンネス(Heike Kamerlingh Onnes)は1908年にヘリウムの液化に成功した.そのデュワーは1898年に液体水素温度(約20K)までの […]
フェライト磁石と東工大(その2)
磁心に使われる軟磁性材料には鉄損の低いことが求められる.鉄損は交番磁界を与えたときのエネルギー損失だ.これは主に交番磁界によって磁壁が運動することによるヒステリシス損と磁心(鉄心)の中に生じる渦電流による損失からなる. […]
フェライト磁石と東工大(その1)
磁性材料の主な用途は永久磁石と電磁石や変圧器などの磁心だ.永久磁石はいったん磁化されるとその状態が長く保たれるタイプで,強力な永久磁石は保磁力と残留磁束密度が大きい.他方,電磁石や変圧器は磁心とそれに巻き付けて設置された […]
東工大のペロブスカイト研究と誘電体
コンデンサーやPTCサーミスタに応用されているチタン酸バリウム(BaTiO3)や代表的な圧電材料[注1]のPZT(PbZr1-xTixO3)はペロブスカイト型の結晶構造だ[1]. 高温超伝導体として20世紀末に急に脚光を […]
資本主義経済と市場介入
国家が経済を牛耳る計画経済に対し,国民が自由な経済取引を行う自由主義の経済をその対極とすると,その中間にはさまざまな経済システムが存在し得る.政府の介入を最小限に抑えた市場経済では経済活動の自由度が高いが,戦時中の統制経 […]
民主主義の持続可能性
社会を記述するには,技術水準,統治方式,経済体制がキーワードだ.石器時代から農耕社会を経て工業社会への進化は技術水準による区分だ.封建制や民主制は統治方式の相違,資本主義や共産主義は経済体制による区別だ.太古からの歴史を […]
歴史に学ぶ民主主義への道
独裁権力を掌中に収めるには平和裏での合法的な手続きで可能だが,封建制や全体主義的独裁体制から民主主義への移行には革命あるいは敗戦による体制崩壊が効果的だったようだ.事実,イギリスとフランスは革命とクーデターを繰り返して封 […]
自動車技術のイノベーション
19世紀に優勢だった蒸気自動車と電気自動車に代わって,20世紀にガソリン自動車が優位となったのは技術革新が急速に進んだからだ.ガソリン自動車が登場したときには,エンジンの始動が面倒で危険だった.エンジンのクランクシャフト […]
イノベーションを生みだすもの(その4)
18歳の学生であったウィリアム・パーキン(William Henry Perkin, 1838 - 1907)はアリル・トレイジンからキニーネを合成する実験を試みたが,うまくいかず,その理由を調べるために構造の単純な硫酸 […]
イノベーションを生みだすもの(その3)
トーマス・エジソン(Thomas Alva Edison, 1847 - 1931)の炭素フィラメント材料の開発やアルヴィン・ミタッシュ(Alwin Mittasch, 1869 - 1953)のアンモニア合成触媒開発は […]
イノベーションを生みだすもの(その2)
アイデア主導型のイノベーションは経験的知識あるいはその時代までに得られている一般的な科学的知識の応用がほとんどだ.第1次産業革命と第3次産業革命ではほぼすべてのイノベーション,第2次産業革命ではすべてではないが,かなりの […]
イノベーションを生みだすもの(その1)
イノベーションにはさまざまな革新が含まれる.新技術を開発して新規な製品を創出する技術革新がイノベーションにおいて重要であることに間違いはないが,その領域のみに限定するのは狭い見方だ.製造や販売においても生産性を高めるイノ […]
産業革命の諸段階と新しい資本主義
収入が増えて購買力が高まり,質の高い商品を購入するようになって生活水準が向上する.実際にパソコンやスマホの性能は年々高まり,自動車もモデルチェンジ毎に安全性や利便性の向上がみられ,果物などの農作物も品種改良が進み,医薬品 […]
SF小説から未来技術を予測する
ジュール・ヴェルヌが1863年に描いた100年後の世界は産業科学偏重の芸術軽視社会だ.応用化学に代表される科学工学が重視され,重要なものは実利で,文学や芸術は忘れ去られた世界だ.芸術に関心を持つものは世の中の余計物であり […]
田園都市計画と大岡山
1912年の桜新町の分譲に始まり,1920年代には東京西郊の住宅地の開発が本格的となった.その結果,都心から郊外への住民移動が起こって人口は急増した. 表1.東京西郊で住宅開発された村の人口増加率[1] 村 名 1920 […]
ろうそくの科学と照明技術
1791年に貧困家庭に生まれたマイケル・ファラデー(Michael Faraday)は製本業の年季奉公を経て,ハンフリー・デービー(Humphry Davy)に雇われ,1813年に王立研究所(Royal Institut […]
タカタはなぜ破綻したのか
自動車の衝突安全についてまず行われたことは,衝突事故が起こって自動車が急減速したときの衝撃を和らげるために,車両の前部と後部にエネルギー吸収構造(クラッシャブルゾーン)を設けることだった[1].軽微な事故でも自動車のフロ […]
タイヤの脱落事故とセラミックスの国際規格
大型車のタイヤが走行中に外れる事故がここ10年で12倍に急増したとのニュースがあった.冬用タイヤに交換した際の不備が主な原因とされ,急増の背景には2010年のネジ規格の変更があるとも指摘されている.海外に輸出しやすくする […]
熱機関の進化とセラミックエンジン
セラミックエンジンが注目され始めたのは1970年代からだ.ガスタービンエンジンの熱効率を高めるために耐熱性に優れたセラミックスを応用しようとするものであった.これは蒸気機関の開発以来,継続してきた熱機関の性能向上に係わる […]
電気自動車と永久磁石と超伝導
ガストン・プランテ(Gaston Planté)による鉛蓄電池の発明は1859年だったが,充電式電池を搭載した電気自動車の実用化が進んだのは1880年代になってからだった.ニューヨークでトーマス・エジソン(Thomas […]
自動車の排ガス処理と奇妙な解決策
自動車の排ガスで主に問題となるのは,NOx(ノックス)と黒煙だ. NOxはエンジンの内部で高温となった窒素ガスと酸素ガスが反応して形成され,反応温度が高いとその生成量も多くなる.エンジンの燃焼室では主に一酸化窒素(NO) […]
揺れ動く自動車の新動力と電動車
10年ほど前に自動車技術の解説記事を書いたことがある[1].エンジン部品としてのセラミックスや金属部品の加工工程に用いられるセラミックスについての解説が中心だが,安全にかかわる電子技術と動力技術の動向についても付記してお […]
自動運転車と近未来社会
未来予測や達成目標に向けてのビジネスプランがその通りに実現されることは稀なことだ.単純化された前提の上に構築されるものなので想定外の問題が発生することが普通だからだ.間違いを犯すことが特徴の人間に無謬性を期待すること自体 […]
予告:Sunday Essayを再開します
昨秋,掲載したSunday Essayを再開します.昨年の続きなので第13回からの始まりです.内容は自動車技術に関係した話です.公開日になれば,下記のリンクからも閲覧できます. 13.自動運転車と近未来社会 (2022年 […]
ダンバー数を超えるとき
複数の個体が集まって,互いに協力する群れ集団を形成する場合には仲間同士が「我ら」で,他の群れは敵対する「奴ら」と区分される.オオカミの群れは,縄張りに侵入した部外者のオオカミを執拗に攻撃して追い払い,チンパンジーは随時, […]