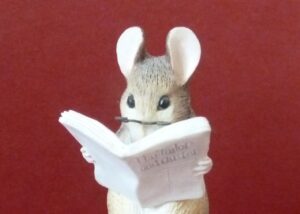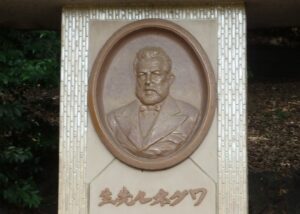寄稿・投稿
国際単位系のあれこれ4
単位はなぜ必要なのでしょうか。 近所の道を歩いている時に、「パン屋に行きたいのですけど。」と聞かれたとします。その人が間違いなく行かれるように説明しようとします。「ここから50 mほど歩くと右にあります。」とか伝えま […]
電気の世界に想いを馳せる
原子を構成する原子核も電子も電気を帯びているから現実の世界は電気に満ち溢れているのだが,電気の正体は永いこと露わにならなかった.正負の電荷はクーロン力で近づくのですぐに中和されてしまい,電気の存在はひっそりと隠されていた […]
庭の自然を楽しむ-9 シジュウカラ
庭に小鳥を呼ぶ楽しみを終わるに当たって,シジュウカラを紹介したい. シジュウカラはスズメほどの大きさの小鳥である.白いほっぺたに黒いネクタイが特徴で,よく見ると後頭部は黄色から緑がかった色をしており,綺麗な鳥である […]
庭の自然を楽しむ-8 メジロのつがい
ケージの中に餌を置くようになったらメジロは安心して餌を食べられるようになった.メジロが一羽で訪れることもあり,二羽で訪れることもある.二羽のメジロの一羽が餌を食べているともう一羽はケージの外に待っている.もしかしたら“ […]
オンネスとベドノルツに学ぶ大発見への道
デュワー(James Dewar)は1896年に水素の液化に成功し,オンネス(Heike Kamerlingh Onnes)は1908年にヘリウムの液化に成功した.そのデュワーは1898年に液体水素温度(約20K)までの […]
庭の自然を楽しむ-7 ヒヨドリとの争い
メジロに強敵が現れた.メジロより遙かに大きいヒヨドリである.ヒヨドリはハトより少し小さい,尾が長い野鳥であり,「ピーヨ,ピーヨ」と大きな声で鳴く.ヒヨドリもメジロと同じように花の蜜などの甘い液体を好む.そのヒヨドリがそ […]
フェライト磁石と東工大(その2)
磁心に使われる軟磁性材料には鉄損の低いことが求められる.鉄損は交番磁界を与えたときのエネルギー損失だ.これは主に交番磁界によって磁壁が運動することによるヒステリシス損と磁心(鉄心)の中に生じる渦電流による損失からなる. […]
国際単位系のあれこれ3
テレビの寸法は「50型」などと表しています。皆さんご存知と思いますが、これは画面対角線の寸法をinchを単位とした数字です。その結果、イメージとしては大きさが頭に浮かぶのですが、実際に自分の家の棚に収まるかなどは別途寸 […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その7
スキューバの思い出その3 その他 【ダビング雑誌に登場】 月刊ダイバーというダイビングの雑誌が,今は休刊になってしまっていますがありました。このダイバー誌から取材をしたいとのことで海の修復の話をしました。見開き2ページで […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その6
スキューバの思い出その2 海外編 今まで,国内ばかりのダイビングでしたので,海外も潜ってみないととまず選んだのがオーストラリア グレートグレートバリアリーフでした。 【グレートバリアリーフ】 オーストラリアのケアンズに […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その5
スキューバの思い出その1 国内版 スキューバでは色々な思い出があります。多くの思い出の中で特に印象に残っていることをお話したく思います。 【石西礁湖のサンゴ礁】 初めは,深く潜りたい,潜った方がカッコいいと何となく思っ […]
フェライト磁石と東工大(その1)
磁性材料の主な用途は永久磁石と電磁石や変圧器などの磁心だ.永久磁石はいったん磁化されるとその状態が長く保たれるタイプで,強力な永久磁石は保磁力と残留磁束密度が大きい.他方,電磁石や変圧器は磁心とそれに巻き付けて設置された […]
庭の自然を楽しむ-6 メジロを呼ぶ
冬場,12月〜3月までの間,小鳥たちの餌が少なくなる.さらに,冬場は花が少なくなり,庭が寂しくなる.そこで,庭に小さな小鳥の餌台を作り小鳥を庭に呼べば,庭が賑やかになると考えた.小鳥の細かい動作を見ているだけでも新しい […]
溝口さんぽ(No.14お寺さんー前編)
1月の「溝口さんぽ」では、いつも散歩している範囲にある神社について紹介しました。今月は同様に寺院について紹介することにします。今回も各地区にある寺院を順に紹介ということで、今月はその前編になります。まずは住んでいる溝口 […]
たつひとの富士山 その12:2023年富士登山ツアー申込み
2023年の「たつひとの富士山」のスタートです。 昨年は,11月にオーストラリア シドニー近郊のブルーマウンテンのトレッキングをしてきました。その話を「たつひとの富士山」の番外編としてアップしようと思いましたが,この富 […]
国際単位系のあれこれ2
昔、国際的な取引の契約の話を読んだことがあります。交渉の中で相手の欧州企業から「問題が発生した時は日本で裁判する」という提案を受け、喜んで受け入れました。取引の中で実際に問題が発生し、裁判にすると相手に伝えたところ、提 […]
東工大のペロブスカイト研究と誘電体
コンデンサーやPTCサーミスタに応用されているチタン酸バリウム(BaTiO3)や代表的な圧電材料[注1]のPZT(PbZr1-xTixO3)はペロブスカイト型の結晶構造だ[1]. 高温超伝導体として20世紀末に急に脚光を […]
国際単位系のあれこれ1
技術的な仕事をしているかどうかにかかわらず、ほとんどの方は毎日のようにメートル、秒、グラムなどの単位を使っていると思います。これらの単位にはいろいろな決まりがあります。しかしこの決まりがどうなっているかご存知の方は少な […]
溝口さんぽ(No.13新年の神社回り)
”溝口さんぽ”も2年目を迎えました。今年もよろしくお願いします。さて今回は、新年になりましたので、元旦の朝、これまでの散歩コースなどにある各地区の神社をめぐってみることにしました。住んでいる地域の鎮守社は溝口神社なので […]
2023年の年頭あいさつ (企画担当・副会長)
あけましておめでとうございます。無機材会 本年もよろしくお願いいたします。 企画を担当したのが2019年からです。当初は対面であった工場見学会や企業セミナーも,その後のコロナ禍の影響で,リモート Zoomでの開催となっ […]
溝口さんぽ(No.12師走の街)
早いもので2022年の最終月である12月になりました。師走も中旬になり、ここのところ朝晩の冷え込みや曇天時の雲の寒々とした様子が冬の雰囲気になってきました。一方、街にはクリスマスムードがあふれています。溝口の駅前は東急 […]
たつひとの富士山 その11: 機中からみた富士山と久しぶりにみる川崎からの富士山
2022年12月2日【石垣島へ向かう機中から見た富士山】 前日,朝にオーストラリアから帰国して,次の日に長男の結婚式で沖縄石垣島へ向かう機中からみた富士山です。機長さんのアナウンスで頂上が雲の上に飛び出した富士山を見るこ […]
溝口さんぽ(No.11秋の風情)
前回の記事にも書きましたが、今年はたしかに例年よりも秋の深まりが早いようですね。11月に入るとともに樹々の葉が色づき始めました。下の写真は、マンションの庭木ですが、11月2日の時点でもうすっかり色づいています。今日は既 […]
合気道エッセイ 目次
合気道エッセイ その1 「合気道の合気のお話」 合気道エッセイ その2 「その時私は」物語 「合気道の合気のお話」 合気道エッセイ その1 合気道あいきどうの名前だけは頭の片隅にある人への合気道の合気のお話です。今 […]
たつひとの富士山 その十: 川崎からみる富士山初冠雪
2022年10月25日 【富士山】 朝から寒く,11月下旬の気温とか。外をみると富士山が雪化粧です。 【あそこに登ってきたんだ】 昨年までは富士山をみて,あそこまで登る人がいるんだと眺めていました。今は「あそこに登ってき […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その4
合気道エッセイ: 合気道とスキューバ 合気道をやるうえで極意となる丹田や重力のことなど,スキューバは色々なことを考えるきっかけとなりました。そんなお話をしたく思います。 【中性浮力】 「中性浮力」(neutral bu […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その3
【ダイビングを経験し新たにわかったこと】 普段,陸上に生きている我々には,中々体感できないことをこのスキューバで知りました。そのお話をしたく思います。考えてみればそうなんですけれどその場に遭遇しないとなかなか実知識として […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その2
【そもそものきっかけ】 当時は,製鉄所の鋼を作る部署で,1600度の高温の溶鋼を精錬する容器をメインテナンスする仕事をしていました。高温の鋼を入れる容器には耐火物を使います。一方,鋼を作るときに副産物として発生するスラグ […]
「その時私は」物語:たつひとのスキューバ その1
【はじめに】 40代後半になってスキューバ,スキューバダイビングを始めました。それも仕事関係です。45歳以上は,始めるにあたって医者の診断書がいる様になります。今回の「その時私は」物語では,スキューバを始めるきっかけのお […]