北里柴三郎と伝染病研究所の跡地を辿る
北里柴三郎は1871年に古城医学所 (1872年に改称して熊本医学校) に入学してオランダ人医師マンスフェルト (Constant Mansveldt) に学び,1875年に東京医学校 (現在の東京大学医学部) に進学した[注1].北里は熊本ではマンスフェルトに眼を掛けられたが,東京医学校では教師陣に眼を付けられた.教師の居丈高な態度と倨傲の物言いに反発した北里は授業中に公然と教師を批判したばかりでなく,教師の論文の不備も指摘したからだ[1].そして在学中に雄弁会「同盟社」を立ち上げ,毎週土曜日に演説会を開いた.「医道論(1878)」は医の基本は予防にあるという信念を掲げた演説原稿である.
北里は予科3年,本科5年の過程を経て1883年に東京大学を卒業して医学士となり,内務省衛生局に勤務した.局長は緒方洪庵の適塾で福沢諭吉の後任として塾頭を務め,長崎精得館でマンスフェルトとともに医学教育に取り組んだのち,1874年に東京医学校の校長に就任し,1875年に衛生局を創設した長与専斎である.
北里は衛生局・東京衛生試験所で細菌学の研究に取り組んだ.指導者は熊本医学校で北里とともに学び,1884年にドイツ留学から帰国して東京大学医学部・衛生学講座の講師になっていた緒方正規である.緒方は1885年に衛生局御用掛を兼務し,北里はその助手についた.熊本医学校で北里の同級だった緒方は北里の恩師になったのだ.
東京衛生試験所の北里は,まず1885年の4月に鳥の集団死の原因究明に取り組み,パスツール (Louis Pasteur) が1880年に発見したニワトリ・コレラ菌であることを特定した.9月には長崎で大流行した原因不明の伝染病の調査に赴いて業績をあげた.ロベルト・コッホ (Robert Koch) が1883年に発見したコレラ菌を日本で初めて検出し,他の地域に拡大することなく終息させたのだ.長与局長は北里のドイツ留学を内務省に申し入れた.
1886年にドイツのベルリン大学へ留学した北里はロベルト・コッホに師事し,1889年に破傷風菌のみを取り出す「破傷風菌純粋培養法」に成功し,1890年には破傷風菌抗毒素 (抗毒素とは体内に備わった免疫体のことで,破傷風菌が作り出す毒素に対抗する) を発見して血清療法を開発した.嫌気性菌の培養装置の開発と死亡率80%であった破傷風の治療法の確立である.
そしてベーリング (Emil Adolf von Behring) と連名の論文「動物におけるジフテリア免疫と破傷風免疫の成立について」を1890年に発表した.この論文に掲載された動物実験のデータは破傷風の免疫をもったウサギの血清が破傷風の予防及び治療に応用できることを明らかにした北里の行った動物実験であり,ベーリングによるジフテリアの実験報告は含まれていなかったのだが,ベーリングはこの論文で第1回 (1901年) ノーベル生理学・医学賞を受賞した[1].なお,ベーリングのジフテリア研究は,コッホの指示によって北里の破傷風免疫と血清療法の研究をジフテリアに応用したもので,ジフテリアの動物実験データはその翌週に発表された論文に掲載された[2].
1890年にコッホは結核の治療薬「ツベルクリン」の創製を発表し,世界各国から派遣されてくる研究者の参加依頼をすべて断り,北里を研究の中心メンバーに据えて臨床応用に向けた研究開発を進めた[注2].北里は皇室からの下賜金で留学期間を延長し,ツベルクリン研究に取り組んだのだ.
世界的な研究成果をあげた北里がケンブリッジ大学,ジョンズ・ホプキンズ大学,ペンシルベニア大学などからの高待遇での招聘をすべて断って帰国したのは1892年のことである.しかし,帰国した北里を迎え入れる研究機関はなく,無職・無給のまま半年が過ぎた.内務省衛生局長の後藤新平と衆議院議員の長谷川泰は伝染病研究所設立を政府に働きかけたが,それには審議と予算獲得のための長い交渉期間が必要だった.そこで長与専斎が福澤諭吉に働きかけて私立の伝染病研究所が発足したのだ.
福沢諭吉が提供した芝公園内の借地に二階建て,上下6室,建坪十余坪の小規模な伝染病研究所が建設され,北里はそこで伝染病研究に取り組んだ[3].実験器具などは森村財閥の森村市左衛門の寄付によって賄われ,研究費については伝染病研究所の運営母体に名乗り出た大日本私立衛生会 (副会頭・長与専斎) からの支援を受けた.伝染病研究所発祥の地の石碑は御成門駅の出口付近にある.

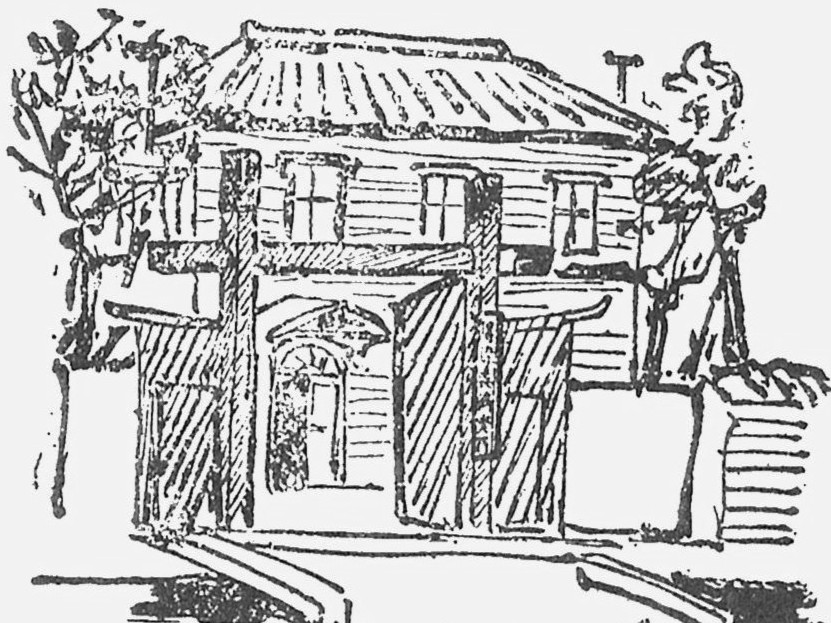
(北里柴三郎傳[3]より転載)
1893年には伝染病研究所 (大日本私立衛生会附属伝染病研究所) が手狭になったので,芝区愛宕町 (現在の西新橋三丁目22-5) にある内務省用地への移転を計画すると,病院に感染者が担ぎ込まれると迷惑との理由で建設反対運動が起きた[注3].しかし,福沢諭吉の説得と後藤新平の謀略が功を奏して反対運動は沈静化し,1894年2月に二階建て本館,二階建て病室,動物室,消毒室など全8棟からなる研究所は完成した[1].そして始まったのがジフテリア抗血清治療 (治癒率は90%) である[2].
1899年に「私立伝染病研究所」は後藤新平の助言もあって国に献納され,内務省管轄の「国立伝染病研究所」となったのだが,この後藤の助言は後に禍根を残すことになる.なお,芝公園内の建物 (旧伝染病研究所) はその後しばらく北里の住居として使われた[4].
余談だが,1894年6月に北里はペストの蔓延していた香港に内務省から調査研究するよう青山胤通 (帝国大学医科大学教授) とともに派遣され,青山はペストに罹患し,北里はペスト菌を発見している.当時のペスト患者の致死率は95%以上であった[注4].
福澤諭吉が所有する広尾の土地を北里に提供し,森村市左衛門が運営資金を寄付して結核専門病院「土筆ケ岡養生園」が開園したのは1893年のことである[1, 4].この建設と運営は腹心の弟子である田端重晟に任せ,「政府というものはいつ考えが変わるか分からない.足元の明るいうちに資金を貯めて独立する用意をしておくように」との言葉を残した[1].なお,伝染病研究所の移転計画とは異なり土筆ケ岡養生園の建設には反対運動は起こらなかった.そして患者が全国からひっきりなしに詰めかけるほどの人気を博し,通院患者用の常設宿が病院の周囲に立ち並んだ.
養生園では北里の開発した免疫血清療法が行われた.まずは1894年に土筆ケ岡養生園で製造したコレラの免疫血清を用いた初の免疫血清療法が,東京府広尾病院に入院する193人のコレラ患者に対して行われた[1].土筆ケ岡養生園は戦災によって焼失し,その跡地には北里大学北里研究所病院が建てられた.
1906年に国立伝染病研究所は白金台に移転した.愛宕町の525坪の敷地では手狭になったので,白金台の1万9千坪の敷地に建坪3400坪の建造物が建設されたのだ[1, 3].これが現在の東京大学医科学研究所である.その入り口近くにある近代医科学記念館 (2001年開設) には,伝染病研究所の歴史的資料が保存されている.そして近代医科学記念館の向かいにあるのは,1938年に設立された公衆衛生院の建物で,2018年に改修されて港区立郷土歴史館となった.





1914年に政府は国立伝染病研究所の所管を文部省に移管し,東京帝国大学の下部組織にする方針を発表した.それに反発して所長を辞任した北里は私立北里研究所 (現在の学校法人北里研究所,北里大学の母体) を港区白金に設立し,狂犬病,インフルエンザ,赤痢,発疹チフスなどの血清開発に取り組んだ.
医者を育成するための教育機関ならば学問や教育を司る文部省の所管が相応しいのだが,患者を救命するための研究機関ならば公衆衛生を担う内務省の所管が相応しいと北里は考えた[1].文部省への移管を画策した青山胤通にとって,北里の辞任は織りこみ済みであったが,他の研究者も追従して辞任することは想定外であった.大学教授として迎えるなどの好条件を示せば容易に留任に応じると高をくくっていたからだ[1].
私立北里研究所の創設にあたっては,福沢の遺言にしたがって田端重晟 (養生園事務長) が積み立てた30万円 (現在の約30億円に相当) と北里の個人資産が充てられ,土筆ケ岡養生園の裏手にある水の深さ3メートルほどの沼地に研究所は建てられた[1, 4].後藤新平の助言は禍根を残したのだが,福沢諭吉の遺言はそれを織りこみ済みだったのだ.北里研究所の北里柴三郎記念博物館は,1964年に開設された「北里柴三郎遺品室」を祖とするもので,2017年から現在の場所で遺品などが展示されている.なお,北里研究所に鎮座するコッホ・北里神社の由来は1910年にコッホ祠を白金台の伝染病研究所内に建て,それを1915年に北里研究所内に招来したことが始まりだ.1931年に北里が逝去すると門下生らはコッホ祠の傍らに北里祠を設けたのだが,戦災によって北里祠は焼失し,難を免れたコッホ祠に合祀して現在に至っている.



1916年に文部省に移管された「国立伝染病研究所」は,東京帝国大学附置伝染病研究所 (所長は青山胤通) となったが,1947年に厚生省所管の国立予防衛生研究所 (現在の国立感染症研究所) が設置されると検査等に係る本研究所職員の約半数が移籍し,1967年に東京大学医科学研究所に改組された.なお,国立感染症研究所は1992年に移転し,現在の本部は戸山の陸軍軍医学校跡地にある.その後,1917年に慶應義塾大学部医学科が誕生すると福沢諭吉の恩顧に報いるため北里柴三郎は医学科長 (1919年に医学部長) に就任した[注5].北里は1923年に日本医師会が設立されるとその初代会長にも就任した.
ところで1914年に政府が国立伝染病研究所を東京帝国大学の下部組織にする方針を発表すると,北里は辞任し新たに私立北里研究所を設立したのは,東京医学校で教師陣に眼を付けられていたからだけではない.また,ツベルクリン研究のために帝国大学から派遣された研究者が,コッホに「余の下には北里が居ることを日本政府は忘れているのか」と言って門前払いされたからだけでもない.大学とは以下のような確執もあったからだ.
東京大学・衛生学教室の緒方正規は1885年に脚気菌を発見したと発表した[注6].また,ユトレヒト大学のペーケルハーリング (Cornelis Adrianus Pekelharing) も1887年に同様の発表を行った.しかし,この実験報告を読んだ北里柴三郎は脚気菌を分離培養する際の実験手法にいずれも大きな不備のあることを指摘し,パーケルハーリングと緒方が発見したバクテリアは脚気の病原菌ではないと結論した.実際,パーケルハーリングが培養した菌株を追試した北里は,それがどこにでもいるブドウ球菌であることを確認した.しかし,北里の指摘は思わぬ波紋を呼んだ.緒方は北里の恩師であり,北里の指摘は恩を仇で返す不忠者として批判の的となったのだ.帝国大学総長の加藤弘之は「子弟の道を解せざるもの」と叱責し,陸軍軍医の森林太郎 (森鴎外) は「北里は識を重んぜんとする余りに果ては情を忘れたり」と指摘した[5].少なくとも当時の帝国大学では学問の自由や真理の探究より,私情が優先されていたようである.
北里研究所では1894年に北里柴三郎がペスト菌を発見し,1897年に志賀潔は赤痢菌を発見するといった学問的成果を上げていたのだが,それはコッホの四原則に則った真理の追究が行われていたのであり,私情に配慮したものではなかった[注7].北里の門下生には,1910年には梅毒を治療する化学薬品サルバルサンをドイツ留学時にパウル・エールリヒ (Paul Ehrlich) のもとで開発した秦佐八郎,1898年に図書係兼見習い助手として伝染病研究所に入所し,その後アメリカに渡航して蛇毒や黄熱病の研究に携わった野口英世らの名も知られている[1, 4].
当時の帝国大学が成果を上げていないと言うのは極論だ.北里柴三郎や志賀潔らを輩出した優れた教育機関であることに疑義はない.研究を通じた教育が大学では適切に行われ,社会的な使命を果たしてきたことにも疑いはない.しかし,患者を救命することを社会的使命として最優先事項とするならば,それを大学に期待すること自体が的外れなのだ.実際,コッホが炭疽菌 (1876年),結核菌 (1882年),コレラ菌 (1883年) などの病原菌を短期間に特定したのは,ベルリン大学奉職前のウォルシュタインの地区保険医官および王立保険庁に在籍していた時期である[2].当時の帝国大学における最優先事項が何かは明らかではないが,陸軍医務局の森林太郎局長は「私立の北里研究所が盛んになると政府の役人は困るのだ」と北里研究所のその後の所長になる北島多一に語っている[1].
当時の帝国大学が社会的使命に関して「選択と集中」を徹底していたとは言い難いが,曖昧な戦略によって「二兎を追うものは一兎をも得ず」状態にまで堕ちたのでもなかった.しかし,二兎を得られないことは役人とその意を汲む大学関係者を困らせたようだ.二兎を得るための方策が1914年の政府の決定だ.M&Aによる敵対的買収 (費用は紙切れ1枚) は帝国大学と文部省の価値向上に寄与した.
北里が医学界に貢献する大きな成果をあげたのは,もちろん本人の資質と努力に負うところは大きいのであるが,福沢諭吉や長与専斎をはじめとする多くの支援者に支えられたことは否めない.だが,私情を排して真理を追究し,社会的使命を全うしようとする姿勢は政府 (文部省) の役人や帝国大学には不都合であったことも否めない.さまざまな力の釣り合いの中で北里柴三郎の人生は翻弄されたのだ.出る杭が打たれるのは日本国の常であるが,北里の場合には支援者の存在が救いだったようだ.
[注1] 現在の東京大学医学部は,1858年に開設された種痘所が起源である.1860年に幕府直轄となった後,西洋医学所 (1861年),医学所 (1863年),大病院 (1868年),医学校兼病院 (1869年),大学東校 (1869年),東校 (1871年),第一大学区医学校 (1872年),東京医学校 (1874年),東京大学医学部 (1877年),帝国大学医科大学 (1886年),東京帝国大学医科大学 (1897年),東京帝国大学医学部 (1919年),東京大学医学部 (1947年) と名称は変化した.
[注2] ツベルクリンは結核菌培養ろ液から精製した抗原で,モルモットでは結核の治療効果が認められた.しかし,ヒトでは結核菌への抵抗力は高まったものの結核の治療効果は認められなかった.その後,パスツール研究所で弱毒化した結核菌を予防接種に用いる手法が開発され,1921年にBCGワクチンが実用化された.なお,結核の治療には結核菌を攻撃するストレプトマイシンなどの抗生物質の投与が効果的である.ストレプトマイシンをワクスマン (Selman Abraham Waksman) が発見したのは1944年であった.病気の原因究明,予防法の開発,病気の治療法の開発は一朝一夕に進むものではなかったのだ.
[注3] 読売新聞の報道 (1893年7月12日付) によれば,伝染病研究所建設反対運動の旗手は帝国大学初代総長の渡辺洪基や衆議院議員の末松謙澄らである[1].そして伝染病研究所反対運動の裏には現内閣の意向があり,北里に批判的な帝国大学医科大学の教授たちが現内閣閣僚に働きかけて行われたことが示唆されている.それは帝国大学医科大学の伝染病研究所設立構想が「わが国にはすでに北里の伝染病研究所がある」との理由であえなく廃案となって間もない時期のことであった.
[注4] ペストはネズミに流行する伝染病だが蚤が媒介してヒトに感染する.ペスト菌が身体に侵入すると首や脇のリンパ節が腫脹する.ペスト菌の増殖を抑えるためリンパ節が腫れるのだが,その腫脹が激痛を起こす.そして皮膚に黒い斑点が現れ,高熱を発する症状が現れる.この状態が腺ペストで接触感染によってヒトからヒトに感染する.腺ペストが進行すると肺ペストになる.肺ペストの患者は咳やくしゃみで大量のペスト菌を撒き散らし,飛沫感染によってヒトからヒトに感染して肺ペストが発症する.当時の肺ペストの致死率は100%であった.そしてペスト菌が血液に入って起こるのが敗血症ペストだ.全身が黒い痣だらけになって死亡するので黒死病とも呼ばれた.
[注5] 1873年に設立された慶應義塾医学所は英米医学を教授する教育機関であるが,1880年の経営危機によって廃校となった.西南戦争の影響で塾生が激減したのだ.その後,理学分野の学科を新たに設置して総合大学とする議案が何度か持ち上がったのだが,それが実現に向かったのは慶應義塾創立60周年を迎えようとする1916年であった.医学科の創設と薬学などの研究を行う化学科の設立が発表されたのである.そして1917年に誕生した慶應義塾大学部医学科は1920年に大学病院を開設し,1937年には北里記念医学図書館 (信濃町メディアセンター) を開設した.
[注6] 現在では,農芸化学者の鈴木梅太郎が1910年に米糠から脚気予防の有効成分 (オリザニン) を発見したことで,脚気がビタミンB1欠乏症であることはよく知られている.鈴木梅太郎の発見 (動物実験で効果を確認) にもかかわらず脚気死亡者数が減少しなかったのは,当時の医師の間では脚気伝染病説が根強く信じられ,医師による脚気患者への試験治療が行われなかったからだ.実際,海軍軍医総監・高木兼寛は海軍の兵食改革を進め,洋食 (パンまたは麦飯) とすると脚気患者が激減することを1884年の疫学実験 (287日間の航海の兵食に洋食を提供) で実証したのだが,たらふくの白米飯と貧相な副食を陸軍兵食の規則 (1877年の規則では1人1日あたり白米6合に副食費が6銭) として定めていた陸軍はその実験結果を認めようとしなかった[6].そのため日清戦争で陸軍の戦死者数は977人 (さらに戦傷者は3,699人で戦傷死に至った者は293人) に留まったが,陸軍の脚気死亡者数は4,064人 (脚気患者は41,431名) に及んだ.その後,生活が豊かになって白米食の普及が進むと脚気患者数は増大に向かい,患者数の減少は日中戦争での食糧不足と戦後の食生活の変化を待たねばならなかった.
[注7] コッホの四原則は,
(i) ある一定の感染病には一定の微生物 (病原体) が検出できること
(ii) その微生物を分離培養 (純粋培養) できること
(iii) 分離培養した微生物をある動物に感染させて同じ感染症を起こすことができること
(iv) 感染した動物の病巣部から同じ微生物が分離培養できること
である[1].あるいは(i)から(iii)をコッホの三原則とすることもある[5].これらは病気の原因となる病原体を発見したと証明するための必要な条件だ.コッホは固形培地による細菌の純粋培養技術の開発し,1876年には炭疽菌を用いてこの手法を実証した.なお,1857年にヴィルマン (Jean Antoine Villemin) は結核に感染したヒトやウシの検体をウサギに接種すると感染することを実験で確かめ,後にヴィルマンとコッホの菌は同一であることが確認されたのだが,結核菌は1882年にコッホが発見したとされている.これはコッホの原則を満たしたかどうかで判断された[5].
文献
1.上山明博,北里柴三郎 感染症と闘いつづけた男,青土社 (2021).
2.海堂尊,北里柴三郎,筑摩書房 (2022).
3.宮島幹之助,北里研究所編,北里柴三郎伝 復刻版,北里学園 (1987).
4.砂川幸雄,北里柴三郎の生涯,NTT出版 (2003).
5.福田眞人,北里柴三郎 熱と誠があれば,ミネルヴァ書房 (2008).
6.山下政三,鴎外森林太郎と脚気紛争,日本評論社 (2008).


