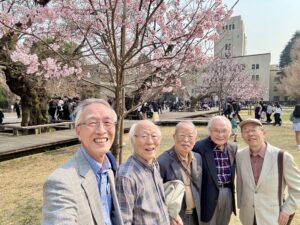万国博覧会の始まりと各国の思惑
万国博覧会 (万博) の始まりは1851年のロンドン万博 (The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) だが,1928年に博覧会国際事務局 (BIE: Bureau International des Expositions) が設立されると万博はBIEが承認した博覧会と定義された[注1].現在の万博では,巨大イベントとしての登録博 (International Registered Exhibitions),規模を縮小して1つの分野にテーマを絞った認定博 (International Recognised Exhibitions) そして園芸博 (International Horticultural Exhibition) がおもなイベントだ[1].
日本での万博開催は1940年に計画されたが無期延期となり,1970年の大阪万博が初の開催である[注2].1970年の大阪万博,2005年の愛知万博そして2025年の大阪万博は登録博,1975-6年に行われた沖縄国際海洋博覧会と1985年に行われたつくば科学万博は認定博,そして1990年に大阪で行われた国際花と緑の博覧会は園芸博である.なお,BIEは国際連盟の下部組織だが,国際連合とは関係がない.
1851年に開催されたロンドン万博の総収入は52万2179ポンド,総支出は33万5742ポンドで,収益は18万6437ポンドであった[2, 3].得られた収益でサウスケンジントンの土地を購入し,ヴィクトリア&アルバート美術館 (Victoria and Albert Museum),サイエンスミュージアム (Science Museum) そしてロンドン自然史博物館 (Natural History Museum) などの施設が後に建設され,会場となったハイドパークに建設した水晶宮 (The Crystal Palace) を設計したパクストン (Joseph Paxton) には5000ポンドの報酬が支払われた[4].
水晶宮は鉄柱と板ガラスで組み立てたプレハブ工法による建造物で,その板ガラスはバーミンガムのチャンス兄弟社 (Chance Brothers and Company) が供給した長さ49インチ,幅10インチのモジュール製品だ[4].なお,ハイドパークとこれらのミュージアムのあるサウスケンジントンをつなぐ道路名は万博に因んだ Exhibition Road である.
ロンドン万博の収益が大きかった理由としては表1のように設定された段階的な入場料とされる[2, 3, 5].その結果,入場料が1シリングの月曜日から木曜日までは地方の農民や労働者階級の人々が訪れて農機具などの機械類に魅惑の目を注ぎ,入場料が5シリングの土曜日には家族連れの中産階級が会場を埋めた.段階的な入場料は階級別の入場日でもあったのだ.
表1.1851年ロンドン万博の入場料[2, 3, 5]
| 入場日 | 入場料 | |
| 最初の2日間 (5/1と5/2) | 1ポンド | |
| 5月5日から24日まで | 5シリング | |
| その後 | 月曜日から木曜日まで | 1シリング |
| 金曜日 | 2シリング6ペンス | |
| 土曜日 | 5シリング (8月以降は2シリング6ペンス) | |
1853-4年のニューヨーク万博 (Exhibition of the Industry of All Nations) は,ロンドン万博をまねて水晶宮 (New York Crystal Palace) と名付けた展示館を建設したものの規模も小さく入場者数も振るわなかった[6].しかし,ヨーロッパの先進的な機械文明と水準の高い文化がアメリカ大陸に紹介されたことで大陸間の交流が促され,アメリカ機械産業の育成には効果的だったとされる[5, 7].
1855年の第1回パリ万博 (Exposition Universelle des produits de l'agriculture, de l'industrie et des beaux-arts de Paris 1855) はクーデターで皇帝に就任したナポレオン3世の統治下で開催された.1848年の二月革命で王政が崩壊して成立した第二共和政のもとで行われた選挙で大統領に就任したルイ・ナポレオンは,1851年のクーデターで独裁体制を樹立し,1852年に始めた第二帝政ではナポレオン3世を名乗っていた[注3].
総計830万フランの赤字に終わった1855年のパリ万博は経営的には失敗だが,イギリスのヴィクトリア女王夫妻が万博に来訪したことで,ナポレオン3世をフランスの正統な君主として認めさせたことは政治的には成功だ[8].フランスはパリ万博を政治活動と捉えていたようだ.
万博での褒賞制度は1851年のロンドン万博でも採用されていたが,1855年のパリ万博では褒章に権威を持たせる工夫がなされた[注4].金メダル,銀メダル,銅メダルの上位にグランプリを設定したのだ[3, 8, 9].出品企業にとってのグランプリ受賞はブランド価値向上に効果的であり,手工業品生産者にとっての恩恵は極めて大きかった.1855年のパリ万博の際に,ナポレオン3世がメドック地区のボルドーワインを1級から5級までに格付けさせたことも,シャトーのブランド価値向上に寄与した[3, 9].フランスはその後,パリ万博を繰り返し開催することで高級ブランドの育成に注力したのだ.
1862年の第2回ロンドン万博 (London International Exhibition of Industry and Art) は日本人がはじめて出会った万博である[3, 6, 10].会場はサウスケンジントンで,現在,そこには自然史博物館が建っている.竹内下野守保徳を正使とする総勢38人の文久遣欧使節団 (日本と修好通商条約を結んでいたイギリスを含む6カ国との開港・開市の延期交渉のため幕府から派遣されていた) が,賓客として万博の開幕式に出席したのだ.
この万博に日本が出品することはなかったが,日本の工芸品が展示された初めての万博でもあった.イギリスの初代公使オールコック (Rutherford Alcock) が自身で集めた日本の収集品 (漆器,陶磁器,銅器,竹製品,紙製品,染織品など) を出品していたからだ.日本の工芸品は一部の専門家に衝撃を与え,ジャポニスムの契機となったのだが,日本使節団は見るに堪えない雑具の展示だと歎いた[10, 11].
第2回ロンドン万博で目論んだのは1851年ロンドン万博のような大きな収益だが,現実の収支はほぼ均衡して剰余金は計上されなかった[12].ロンドンでの万博がこれ以降に開催されていないのは,経費の責任を担う民間組織 (The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) が万博を収益事業と捉えていたからのようだ[4].
1867年の第2回パリ万博 (Exposition Universelle de Paris 1867) は日本が初めて正式参加した万博だが,幕府 (日本大君政府) のみならず,薩摩 (薩摩太守政府)・佐賀 (日本肥後太守政府) 両藩も参加していた[3, 13].江戸幕府は官服 (衣冠と狩衣),武器 (鉄砲,刀,鎧など),書籍 (江戸名所図絵,東海道名所図絵,北斎漫画など),図画 (浮世絵,実測日本地図,油絵) などを出品したが,人気を集めたのは清水卯三郎が展示した江戸柳橋松葉屋の3人の芸者 (おすみ,おかね,おさと) が座敷で煙管をふかしたりするのを土間から眺めるパフォーマンスだった[注5].
薩摩藩の出品物は陶磁器が多かったが,琉球産の砂糖,織物,漆器,泡盛酒や籐細工も出品した.佐賀藩の出品物も陶磁器が大部分だが,刀や緑茶なども出品した.渋沢栄一が御勘定格陸軍附調役として参加して西洋文明を学び,それ日本に取り込む契機となった万博でもあった.
明治政府がはじめて正式に参加した万博が1873年のウィーン万博 (Weltausstellung 1873 in Wien) である[14].展示品の選定はお雇い外国人ワグネルの指導によるもので,日本展示室の入り口には名古屋城の金鯱や高さ185センチの有田焼の花瓶を据えた[11].その奥の中室には各種の工芸品,商家や神輿や土蔵の模型があり,後室には五重塔や大仏模型を据え,その両側に大名屋敷と農家の模型を展示した.このほか会場内に日本庭園を特設して神社を建築し,その前に池を掘って小さな橋を架けた.
日本の出品物の評判は高く,出品物の過半も売れてしまい (博物館への寄贈と有償譲渡を含む),神社と日本庭園も大いに評判となって日本庭園の建物,樹木から石に至るまでの一切はイギリスのアレキサンドル・パーク商社に600ポンドで売却された[14].明治政府のウィーン万博への出展は,展示品の販売に留まらずジャポニスムによる工芸品輸出にも拍車をかけたようだから,輸出振興のための営業活動の成功と見なしてもよいだろう.
しかし,ウィーン万博への参加において輸出振興による目先の利益より重視したのは,ワグネルが建議したヨーロッパの諸工芸の生産技術をウィーン万博派遣者に学ばせる技術伝習であった[15, 16].伝習すべき職種と伝習者,博覧会での座学と製造現場での伝習方法について,ワグネルは26の分野 (実際には30人の伝習者が40以上の職種を伝習した) を明示し,その具体策を提示した.その概要は以下のようだ.
(i) 職種と伝習者の選定:日本の技術改良に役立てるため,日本で行われている工芸の職種を伝習する.
(ii) 博覧会での座学:博覧会に陳列してある製品を観察し,製造方法を記した文献,図解などの調査を行い,製造物の図や雛型を収集する.
(iii) 現場での伝習:職工がオーストリア,ドイツの一定の場所に滞在して製造作業等に取り組む.
職種によって現場での伝習方法は異なるのだが,例えば,藤山種廣はボヘミア州スーヘンタール村でガラス製造の伝習を受け,帰国後,品川硝子製作所で紅色ガラスの製造に取り組んだ[15].エルボーゲン製陶所で陶磁器製造の石膏型についての技術伝習を受けた納富介次郎と河原忠次郎は,帰国後,全国の陶磁器産地から募集した生徒への伝習を通じて,石膏型を用いた陶磁器製造法の普及に貢献した[15].なお,ウィーン万博は19世紀に開催された万博の中で最悪の赤字だったが,これは夏にコレラが流行したため1000万人を見込んでいた来場者が725万人に終わったためだ[3].
アメリカ独立100周年記念として開催された1876年フィラデルフィア万博 (Centennial Exhibition of Arts, Manufactures and Products of the Soil and Mine) は約450万ドルの赤字に終わったが,入場者数は約978万人を数える大規模な万博であった[17].そこに展示されたのは巨大な蒸気機関を含む数々の最新機械に加え,自由の女神 (The Statue of Liberty) の右腕とトーチ部分であった[注6].
自由の女神の胸像が展示されたのは,第三共和政のもとで1878年に行われた第3回パリ万博である.なお,出品した陶磁器をはじめとする美術工芸品が引き金になってジャポニスムが熱狂となった1878年のパリ万博だが,専門家からの指摘は日本工芸品の商業主義による質の低下であった[13].
フランス革命100周年を記念する1889年の第4回パリ万博 (Exposition Universelle de 1889 Paris) ではエッフェル塔が建てられ,セネガルやニューカレドニアなどの植民地村落を再現して実際に先住民を劣等な未開人として住まわせる植民地展示 (人間動物園) も行われた[10, 18].パリ万博における植民地パヴィリオンの展示は1878年以降に拡大し,1931年にはパリ植民地博覧会が開催された[13].
コロンブスのアメリカ大陸到達400周年を記念する1893年のシカゴ万博 (World's Columbian Exposition) では,電気モータ駆動による巨大観覧車 (フェリス・ホイール),動く歩道,高架鉄道が姿をあらわし,人力車椅子も会場内で活躍した[3].フェリス・ホイールは大人気で,会期中に1回50セントの乗り物を145万人が体験し,40万ドルを投資した技師のフェリス (George Washington Gale Ferris) は巨額の財を築いた.そしてスミソニアン協会が中心的な役割を果たした民俗学的集落の展示では,人類進歩の順に集落が配置された[10].ダホメの未開集落とその原住民の展示から文明化されたゲルマン系やケルト系集落に至る並びである.シカゴ万博は帝国主義と人種差別をはっきりと表明した万博であった.
アメリカが1904年に開催したセントルイス万博では,フィリピン諸部族の大規模展示 (フィリピン村) が行われた[6, 19].1898年にハワイを併合し,1899年の米西戦争でフィリピンを獲得したアメリカが行った野蛮な未開人 (ネグリト族やイゴロット族など) と近代教育で進化した準文明人 (先住民の警察兵) の展示である.近代的な教育が非文明状態から人間を解放するとの帝国主義的発想はハーバート・スペンサー (Herbert Spencer) の社会進化論とともに,植民地支配と人種差別を正当化するプロパガンダとして活用され,万博での見世物興行はその可視化であった.
このようにロンドンで初めての万博が開かれてから半世紀も経つと,産業技術奨励の事物教育の場から商業重視の娯楽の場へとその性格も変化した[11].万博が不人気の場合に損失が甚大となることから,入場者数が万博の成否を左右する重要な指標となり,万博への誘客手段として有効な娯楽を提供する遊興施設の設置が重要となったのだ.1900年の第5回パリ万博 (L'Exposition de Paris 1900) では毎日のように饗宴が行われ,イルミネーションや各種の見世物興行が行われた.
ジャポニスムのブームが去ってアール・ヌーヴォー (Art Nouveau) のブームが始まり,日本の展示物の評価も下落した第5回パリ万博だが,そこで人気を博したのは「オッペケペー」を始めとする演目を公演した川上音二郎・貞奴一座だった[3, 20].アメリカとロンドン巡業に続いて行われたパリ万博公演でも,女優・貞奴の人気はとどまることをしらず,「サダヤッコ」の名称を使った多くの商品も販売されたのだ.なお,第5回パリ万博の付属大会として行われたのが第2回オリンピックである[注7].
1851年のロンドン万博は大きな利益を生みだした収益事業であったが,1862年の第2回ロンドン万博の決算収支は芳しくなく,それ以降にロンドンで万博が開催されたことはなかった.1855年の第1回パリ万博は革命政権下での赤字事業だったが,革命政権の国家承認や手工業生産者の高級ブランド化といった実益もあった.しかし,その後に開催された万博の多くは国家が主催する国威発揚を狙った赤字事業である.国威発揚のコストが赤字決算なのだ.
19世紀から20世紀初めに全盛期を迎えた万博の役割は,消費者向けの商品展示や大衆娯楽としての見世物の提供という側面もあるが,植民地主義的な展示を行う帝国主義のプロパガンダでもあった[10].未開から文明への進歩を示す展示によって,文明水準が低い国々を植民地支配することを正当化する帝国主義のプロパガンダを大衆に植え付けるのだ.日本でも帝国主義が台頭した1903年の第5回内国博覧会の学術人類館で,未開の原住民集落の展示が行われた[10, 21, 22].
しかし,20世紀後半になると万博における消費者向けの商品展示と帝国主義的プロパガンダといった役割は縮小し,残ったのは大衆娯楽としての見世物の提供だ.万博の狙いが国威発揚ならば,国際的影響力の低い国が開催することは理にかなっているのだが,事業の成否を決する要素が誘客に有効な大衆娯楽の提供なのだから,事業の成功には大衆への迎合が肝要だ.初めての万博が行われた1851年から現在まで万博の名称は堅持されているが,万博の実態は社会情勢に応じて柔軟に変化し,当初の狙いであった産業技術奨励の事物教育の側面を見出すことはいまや至難の業となっている.
[注1] パリ産業博覧会は1798年から1849年の間に11回開催され,会期・出品者数は増大の一途を辿った[10, 13].この影響で,フランス各地での産業博およびヨーロッパ諸国での産業博も盛んに行われるようになった.この狙いはイギリスの工業製品が自国に浸透するのを防ぎ,国内産業を育成し,自国産業力をアピールすることである.そのため産業博の国際化はイギリスの参加を意味するので保護貿易の立場から強い反対があった.万博の始まりが1851年のロンドン万博だったのは,産業技術力に劣るイギリス以外の国々が産業博の国際化に消極的だったからだ.しかし,1867年のパリ万博でイギリスの産業衰退が如実に示されると,1798年に始まる産業博を先導したフランスこそが万国博の創案者であるとの見解が提示され,イギリス以外の国々も万博開催に積極的に取り組むようになった[11].イギリスで1856年に開発されたベッセマー製鋼法がヨーロッパ諸国で普及し,イギリスとの技術格差を一挙に詰める役割を果たしたのだ.なお,プロイセンのクルップ社は巨大鋼鉄砲をフランスに売り込んだのだが,これを断ったフランスは1870年の普仏戦争でクルップ砲を有するプロイセンに惨敗した.
[注2] 日本では万博開催に先立って,京都博覧会と内国勧業博覧会が行われた.日本で最初の博覧会は1871年に西本願寺で開催された京都博覧会である[9, 23, 24].日本古来の武具,古書画,古陶器などの骨董品を中心に展示され,西本願寺,建仁寺,知恩院,京都市勧業館などを会場として,1928年までに56回開催された.大久保利通が西洋文明を写しとる内国勧業博覧会の開催を企画したのは,殖産興業には大衆の意識改革が肝要と考えたからだ[6, 10, 11].そして第1回の内国勧業博覧会が1877年に上野公園で開催された.第2回内国勧業博覧会は1881年,第3回内国勧業博覧会は1890年で,いずれも開催地は上野公園であった.1895年には第4回内国勧業博覧会が京都で開催され,1903年には最後となった第5回内国勧業博覧会が大阪で開催された.内国勧業博覧会の開催に続くステップは万博の誘致開催だ.1890年亜細亜博覧会および1912年日本大博覧会の計画は頓挫したが,1936年には紀元二千六百年記念日本萬国博覧会を1940年3月15日から8月31日まで東京・月島の埋立地と横浜・山下公園で開催することを正式決定した[25].着々と準備も進み,前売り券の販売も始まったのだが,世界情勢の悪化から1938年7月15日に無期延期と閣議決定された (晴海三丁目に建設された万博事務局棟は1938年9月竣工だが,そのときには万博延期が既に決まっていた).販売済みの前売り券が使用されたのは,1970年の大阪万博と2005年の愛知万博である[25, 26].なお,1940年には東京オリンピック (9月21日~10月6日) と札幌での冬季オリンピック (2月3日~14日) も計画されていたのだが,これも1938年の閣議決定で返上されたので,1964年の東京オリンピックおよび1972年での札幌オリンピックでの入場券の購入は必須になった.そして万国博覧会,東京五輪,札幌五輪がなくなった紀元二千六百年記念行事は大幅に縮小されたが,6月には東亜競技大会 (東京大会と関西大会を開催),11月には国民精神作興大会 (聖矛リレーが行われた) と皇居前広場での記念式典 (神輿太鼓や提灯行列も行われた) などが行われた[25].
[注3] 1789年のバスティーユ襲撃に始まるフランス革命で始まったのは混乱であった.ルイ16世が亡命に失敗した1791年には王権を縮小した立憲王政,1792年には第一共和政が成立した.1793年にはルイ16世とマリーアントワネットが処刑され,1794年には恐怖政治を主導したロベスピエールもテルミドールのクーデターにより失脚して処刑された.対仏大同盟を締結した周辺国との対立によってフランスの混乱はヨーロッパの混乱に波及した.このなかでフランス軍を率いた軍人ナポレオンはヨーロッパをほぼ制圧し,1804年に皇帝に即位した.第一帝政の始まりである.しかし,ロシア遠征に失敗したナポレオンは1814年にエルバ島に幽閉され,その後1815年にエルバ島を脱出して復位 (百日天下) したものの,ワーテルローの戦いで敗北したナポレオンはセントヘレナ島に流された.その後のヨーロッパの国際秩序として構築されたウィーン体制のもとでフランスにはブルボン朝が復活し,ルイ18世が1814年に即位すると反動的な政治が始まった.それを継承したシャルル10世が1830年の七月革命で失脚してイギリスに亡命するとルイ・フィリップが即位したのだが,次第に反動的になったルイ・フィリップも1848年の二月革命で失脚してイギリスに亡命し第二共和制に移行した.第二共和制のもとで行われた選挙で大統領に選出されたルイ・ナポレオンが1851年にクーデターを挙行したのは,現職大統領の再選を禁ずる憲法の規定によって1852年12月に退任が予定されていたからだ.
[注4] オリンピックでは金・銀・銅のメダルが授与されるが,このメダルによる褒賞制度は万博に倣ったものだ.1851年のロンドン万博ではヴィクトリア女王とアルバート公の横顔の胸像が描かれたCouncil Medal (評議員牌) とJurors’ Medal (賞牌) が授与された.1855年のパリ万博では,ナポレオン3世の横顔が描かれたグランプリ・金・銀・銅・選外佳作のメダルが授与され,すべての出展品に値札をつけることも始まった.万博での褒賞制度はその後も続いたのだが,出品企業にとってグランプリの受賞はそのブランド価値を高めるのに効果的であった[3, 8].フランスの銀食器メーカー「クリストフル (Christofle)」とクリスタルガラスメーカー「バカラ (Baccara)」は1855年のパリ万博でグランプリを獲得した.「ルイ・ヴィトン (Louis Vuitton Malletier)」の軽量で丈夫な素材の旅行用トランクは1867年のパリ万博で銅メダルを受賞,「エルメス (Hermès)」の鞍は1878年と1889年のパリ万博でグランプリを獲得した.そして「ティファニー (Tiffany & Co.)」の銀器は1878年のパリ万博で金メダルを獲得し,1889年のパリ万博ではグランプリ受賞した.これらの企業は受賞によってブランド価値を大きく高めたのだが,度重なるパリ万博での褒賞制度によって恩恵を受けた企業の多くがフランスの工芸品製造業者であることは偶然ではなさそうだ.
[注5] 1862年のロンドン万博にオールコックが出品した品々は粗末な雑具であったが,1867年のパリ万博で日本は品質の高い工芸品を選んで出品した.日本の出品物は高い関心を集めたのだが,会期中に売れたのは2割程度に留まった.この原因として考えられたことは,陶磁器などのデザインがヨーロッパ人の嗜好に合わなかったことだ.そこで,1873年のウィーン万博では博覧会事務局付属の磁器製作所で,素焼きの清水焼に本来の清水焼のデザインとは異なる絵画風の絵付けを行って出品した[11].それが功を奏してジャポニスムのブームが起こり,1878年のパリ万博の時期には陶磁器をはじめとする美術工芸品が引き金になってジャポニスムは熱狂となったのだが,その一方で日本工芸品の商業主義による質の低下も専門家からは指摘された[13].一般消費者からは歓迎され,専門家からは批判されたのは,工芸品の輸出振興に向けた明治政府の取り組みが日本固有の独創性を捨て,ヨーロッパの嗜好に合わせたデザインの採用であったからだ.1900年の第5回パリ万博にも日本は継続的に参加して工芸品を中心に出品を続けたのだが,ジャポニスムがマンネリ化し,そのブームが去るにつれて,展示物の評価も次第に下落した.日本の輸出用陶磁器のデザインはヨーロッパの一般消費者向けの顧客ニーズに媚びたマーケティングを重視したのだが,消費者の見る目が肥えることは想定外のことだったようだ.
[注6] ニューヨークにある自由の女神像は彫刻家・バルトルディ (Frédéric Auguste Bartholdi) が設計し,約10年の年月をかけてフランスで制作された高さ46メートルの像だ[27].右腕とトーチ部分は1876年,女神の胸像部は1878年に完成していたが,全体像の完成は1884年である.1885年にフランスからアメリカに船で運搬され,1886年4月に台座が完成するとその上に女神像の組み立てが始まった.組み立てが完了して,ニューヨークのリバティ島での除幕式が行われたのは1886年10月のことである.なお,お台場にある自由の女神像はパリ在住のアメリカ人から1889年にパリ市に返礼として贈られた自由の女神像 (セーヌ川のグルネル橋のたもとに設置されている高さ11.5メートルの像) のレプリカだ.パリの自由の女神は1998年に来日してお台場に設置され,1999年には帰国してしまったが,2000年にそのレプリカがお台場に設置されたのだ.
[注7] 近代オリンピックは1896年のアテネ大会に始まった.古代オリンピックと同じく,女子禁制の大会である.しかし,第2回 (1900年のパリ大会) と第3回 (1904年のセントルイス大会) は同時期に開催された万国博覧会の付属大会であり,女子選手も出場した.第4回 (1908年のロンドン大会) はローマで開催される予定だったが,1906年にイタリアのヴェスヴィオ山が噴火したために開催地が変更され,英仏博覧会との同時開催として行われた.そして日本が初めてオリンピックに参加したのは,第5回大会 (1912年のストックホルム大会) である.
文献
1.Bureau International des Expositions:https://www.bie-paris.org/site/en/
2.松村昌家,水晶宮物語,リブロポート (1986).
3.久島伸昭,万博100の物語,ヨシモトブックス (2022).
4.松村昌家,大英帝国博覧会の歴史,ミネルヴァ書房 (2014).
5.国会図書館,博覧会 近代技術の展示場:https://www.ndl.go.jp/exposition/
6.平野暁臣,図説万博の歴史,小学館クリエイティブ (2017).
7.平野繁臣,国際博覧会歴史事典,内山工房 (1999).
8.鹿島茂,パリ万国博覧会 サン=シモンの鉄の夢,講談社 (2022).
9.稲葉茂勝,渡邉優,万国博覧会,ミネルヴァ書房 (2023).
10.吉見俊哉,博覧会の政治学,中央公論社 (1992).
11.國雄行,博覧会と明治の日本,吉川弘文館 (2010).
12.重富公生,1862年ロンドン万国博覧会に関する一考察 イギリス「最後の」万国博覧会,国民経済雑誌,225 [2] 1-17 (2022).
13.寺本敬子,パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生,思文閣出版 (2017).
14.ペーター・パンツァー,沓澤宣賢,宮田奈奈編,1873年ウィーン万国博覧会,思文閣出版 (2022).
15.藤原隆男,明治前期日本の技術伝習と移転 ウィーン万国博覧会の研究,丸善プラネット (2016).
16.武智ゆり,日本の美を工業化したワグネル,近代日本の創造史,6 18-25 (2008).
17.福田州平,フィラデルフィア万博における諸外国の参加をめぐって,インターカルチュラル,13 95-112 (2015).
18.島村駿,1889 年パリ万国博覧会における先住民と植民地帝国アイデンティティの醸成,クリオ,38 [5] 16-30 (2024).
19.楠元町子,セントルイス万国博覧会と日露戦争,異文化コミュニケーション研究,6 135-150 (2003).
20.井上理恵,川上音二郎と貞奴 II 世界を巡演する,社会評論社 (2015).
21.伊藤真実子,明治日本と万国博覧会,吉川弘文館 (2008).
22.松村瞭,大阪の人類館,東京人類學會雜誌,18 [205] 289-292 (1903).
23.吉田光邦,万国博覧会の研究,思文閣出版 (1986).
24.工藤泰子,明治初期京都の博覧会と観光,京都光華女子大学研究紀要,46 77-100 (2008).
25.夫馬信一,幻の東京五輪・万博1940,原書房 (2016).
26.橋爪紳也,博覧会の世紀 1851-1970,青幻舎 (2021).
27.小田基,「自由の女神」物語,晶文社 (1990).