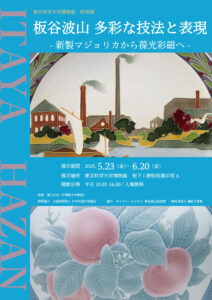豊橋さんぽ(No.17 東海道五十三次の吉田宿)
まだ5月というのに日本各地では夏日どころか真夏日まで報告されることも。本当に春と秋の存在が陰薄くなり、一年を通して四季から二季になりつつあるのを感じさせられます。少し前までは日の当たるところを選んで散歩していたのが、日陰を選ぶようになるとともに、蒸し暑くなってきました。今から散歩で大汗をかくようでは先が思いやられます。
さて、毎日の散歩コースには旧東海道も含まれていますので、今回は東海道五十三次の34番目の宿場であった吉田宿にちなんだ話題を取り上げることにしましょう。旧東海道は豊橋の市域では現在の国道1号線とほぼほぼ同じルートで、特に市街地ではその一部が全く重なるところがあります。また、豊橋市内には吉田宿の外に第33番目の宿場である、二川(ふたがわ)宿があります。この宿場は白須賀宿と吉田宿の距離が長いためその中間地点に設けられたもので、現在でも街道に沿って細長く小集落が残っています。小集落であったために太平洋戦争では空襲の被害がなかったようで、本陣など往時の雰囲気が比較的きれいに保存されていて、本陣は現在、「本陣資料館」として一般公開されています。
一方、吉田宿は吉田藩のご城下に宿場が設けられ、本陣が2軒、脇本陣が1軒と旅籠が38軒あったとのことですので、二川宿よりは賑わっていたようです。しかし、豊橋市の市街は9割ほどが空襲で焼失しているため、昔の面影は全く残っていません。本陣があった辺りは、私が子供の頃は古くからの繁華街として、6月には1か月、夜店が出て賑わいがありました。現在は繁華街が豊橋駅周辺に移動したため、商店街の面影はほとんど感じられなくなってしまいました。豊橋公園に掲示されている案内図(下図)では城を取り囲むように武家屋敷が配置され、その外縁を街道が通っていたようです。城下町には街の東側に東総門(❺)と常夜灯(❼)、一方、西側にも西総門(➏)が設けられていることから、夜間は閉門されていたようです。


安藤広重の東海道五十三次の浮世絵では吉田城と豊川にかかる吉田大橋が描かれています。江戸時代には5街道中でも一番賑わっていた東海道ですが、街道の河にはほとんど橋が架けられておらず、吉田大橋は岡崎城下の矢作大橋、琵琶湖の瀬田の唐橋とともに東海道の三大橋として知られていたようです。実はこの辺りは三河湾の河口から数キロ程度しかなく、吉田大橋の辺りは港としても賑わいがあったようです。あの有名な水戸黄門のTV番組でも吉田湊として登場しています。また、かの有名な松尾芭蕉も貞享4年(1687年)11月11日にこの地の旅籠に投宿し、「寒けれど二人旅寝ぞたのもしき」、「ごを焼いて手拭あぶる寒さ哉」の句を残しています。旧暦の11月11日は現在で言えば12月15日にあたるので、さぞかし寒かったのでしょう。宿泊した旅籠は西の総門の近く(⓫の近く)にあたり、吉田大橋まで歩いて5分ほどの場所です。
(岡田清)


出典:国立国会図書館 デジタルコレクション