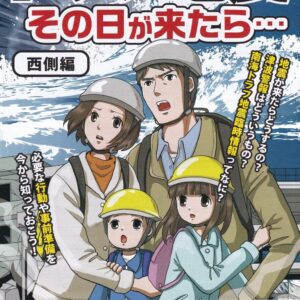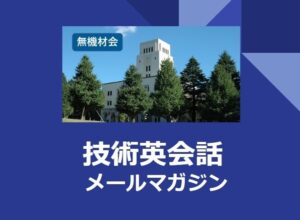「その時私は」物語: わたしの2011年3月11日 その2
【いつも工事中】
記憶をたどって書き込んでいるため,記憶違いなど多々あると思います。
随時,訂正・追加・補正など行っていきますのでご承知ください。
たつひとの合気道場同様,内容はいつも工事中です。
「その時私は」物語: わたしの2011年3月11日 その1 その時
帰宅
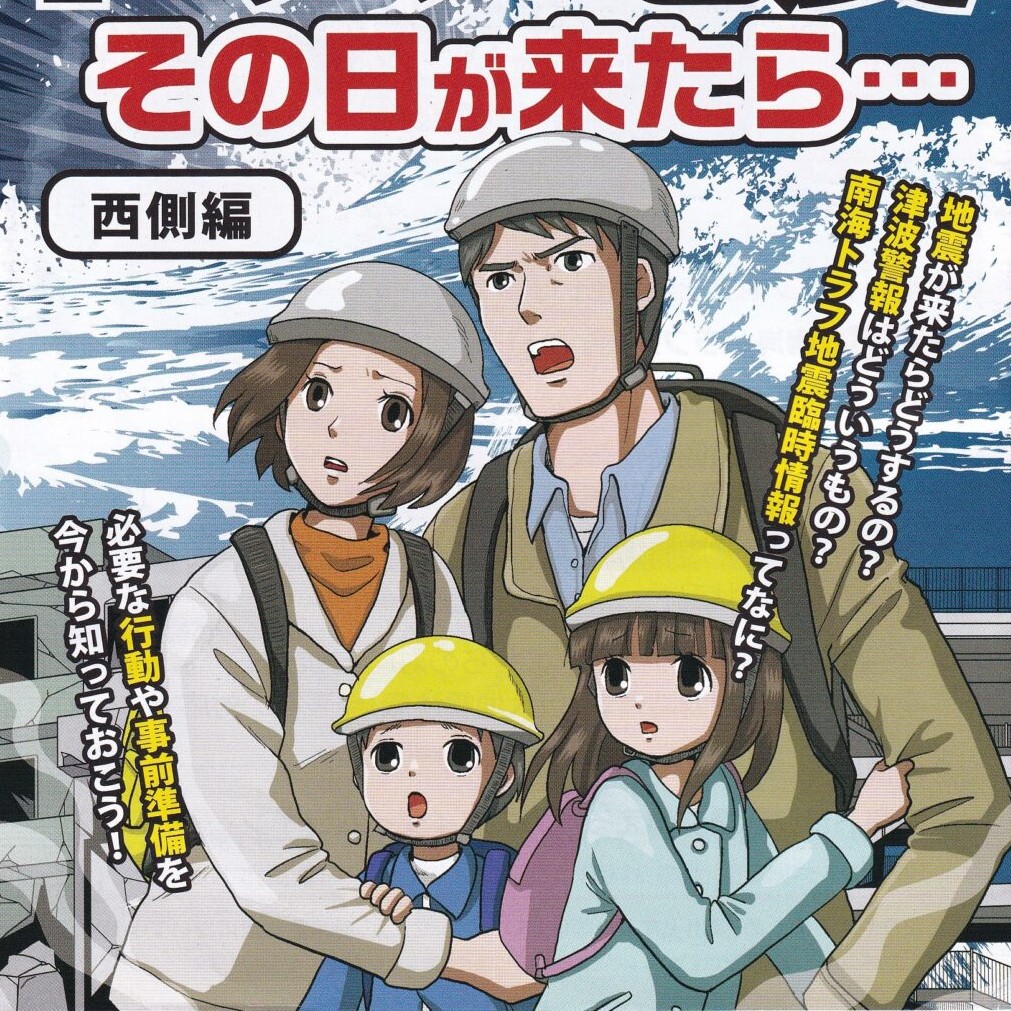
私の留守宅は武蔵小杉,多摩川を渡ったところにあります。一度は,市谷の本社ビルでの泊まりを覚悟したのですが,夜になって東京メトロ南北線の電車が白金高輪まで動き出したとの話が伝わってきました。これだと白金高輪まで行けば,あとは歩けるだろうと,帰宅することに決めました。情報がまだあまり届いていないのか,地下鉄はそれほど混んでいなかったです。
白金高輪駅から地上にでると目黒通りを,目黒にむけて歩き出す人の数は結構いました。目黒駅までは駅で二駅,2kmの距離です。ほどなく目黒駅に着くことができました。幸いなことに,市谷を出る時は運転を見合わせていた東急目黒線は,運転を再開していて,これに乗って武蔵小杉までもどってこれました。ただ,曜日が変わり3月12日となっていました。
後で,聞いた話では,千葉や埼玉の自宅にかなりの人が歩いて帰ったとの話を聞きました。歩きはあったものの運転を再開した電車に乗り継いで帰れたのは,ラッキーだったのかもしれません。
我が家
自宅のある15階建てのマンションに辿り着いたときに,マンションの窓にあかりがついているのを見てホッとしました。一階エントランスから中に入るとマンションの棟の間をつなぐ,1階の通路のコンクリート製縁石同士がぶつかりあって欠けています。このときは気が付きませんでしたが,建物をつなぐエクスパンションジョイントが数か所損傷したとのことでした。大きな建物や複雑な形状の建物では,地震の時に建物の挙動が異なり,その揺れの衝撃を伝わらなくするために建物同士を分割し,その接合面をカバーで覆うもので,これをエクスパンションジョイントといいます。これが損傷したことは,この機構が有効に働いたということになります。
電気は回復していましたが,予想通りエレベーターは動いておらず,地上階から13階まで階段を登らなければなりませんでした。地震になんか負けるものかとの思いで一気に登ったのを覚えています。階段で13階まで登ったのは,この時がはじめてでかつ最後のこととなりました。自宅のマンションでは地震の時,全部で8機あるエレベーターの中での閉じ込め事故は発生しなかったようでよかったです。
家の中はどうなっているか心配でしたが,食器棚など家具はマンション建屋の揺れの向きなどを考慮して並べ変えていたため,食器等が飛散していることもなく我が家としてはよかったのです。ただ息子の部屋では,本棚が横倒しになって壊れていたとのことです。この地震で自宅のある川崎市中原区で観察された震度は震度5弱でした。
この時はまだ,情報がなく津波で太平洋沿岸が大変なことになっているとは,知るよしもありませんでした。
その後
津波の被害だけでも,大変でしたのに,この時は,その4日後,3月15日午前6時14分に起きる福島第一原子力発電所での水素爆発が起きることなど想像もつきませんでした。
【余談 その1:我が家の地震探知機】
我家の地震探知機は,ワイングラスです。洗ったワイングラス🍷を逆さに吊るすラックをキッチンに取り付けています。地震かなと思ったとき,ネットやテレビをつけますが,当地の地震の規模の大きさは,吊るした二つのワイングラスがぶつかる音でわかります。カンカンなったら結構大きな規模の地震です。地震かなと思う程度の揺れは,ワイングラスがぶつかり合いませんが,ゆらゆらと動きます。結構,家の揺れの程度を知るには有効です。
【余談 その2:過去の日本の大震災】
私の父は,1923年11月の生まれです。関東大震災が起きたのはその年の9月1日,実家は東京の目黒区駒場で,祖母は大きなおなかを抱えて逃げたそうです。その関東大震災は,死者・行方不明者が10万人を超える大震災で,1995年1月17日の阪神・淡路大震災が起きるまでは,最大の地震として,9月1日に学校等で避難訓練を行ってきました。2011年の東日本大震災のあと,2016年4月に起きた熊本地震,そして2024年の元旦に起きた能登地震とかなりの頻度で続いている気がしています。
【余談 その3:マンションの地震対応】
2016年4月熊本地震は,マンションが多く被災した地震です。その経験を踏まえ,マンションに特化した防災対策の構築も進んできているようです。私の住むマンションは15階建てですが,全部で600世帯,1600人が住んでいます。その川崎市から指定された避難所は,近くの小学校ですが,生徒数は約650名,規模感から,私の住むマンションの住人が押しかけたらパンクです。
マンションにもマンホールトイレが10個準備していますが,これも1600名の人が使用するとなるとパンクです。そこで,自宅での応急トイレの準備です。水洗トイレは水が必要ですが,水の供給があっても,下水管が壊れている可能性がある場合は,確認が終るまで,トイレの使用はできません。その対策として凝固剤等を使った応急トイレの登場です。最低3日分,可能であれば7日分の備蓄を神奈川県も呼びかけています。
食料や飲料水も同様で,賞味期限のあるものを600世帯,1600人分,数日分をマンションとして用意しておくことは現実的ではありません。これらも自宅での準備をしなければなりません。普段,生活で使用する分を,災害時に備えて多めに買い置きしておく方法,ローリングストックという方法での備蓄が推奨されています。
これらの知識も,たまたまマンションの防災委員になったことがきっかけで,知ることができました。何とかなるだろうと思っても,何とかならないと思った方がいいようです。
以上が,2011年3月11日の「その時私は」物語でした。記憶はだんだん薄れていきます。被災地とは数百キロ離れたところにいた自分でしたが,それなりの話がありました。学生時代に,三陸の田老たろうという村が1896年明治29年の津波で壊滅したところを訪問したときに,山の中腹,かなり上の場所に,記憶と警告を示すため「ここまで津波が来た」との標識がたっていました。その時「ここまで津波がきたんだ」という思いが今でも思い出されます。また来ることがあるのかな,みんなこの標識より,低い場に住んでいるのにと思ったことは,2011年3月に現実になって来たんです。明治の津波より大きい津波が。
「その時私は」物語: わたしの2011年3月11日 その1 その時
高橋達人 (たかはし たつひと) tatsudoc@nifty.com